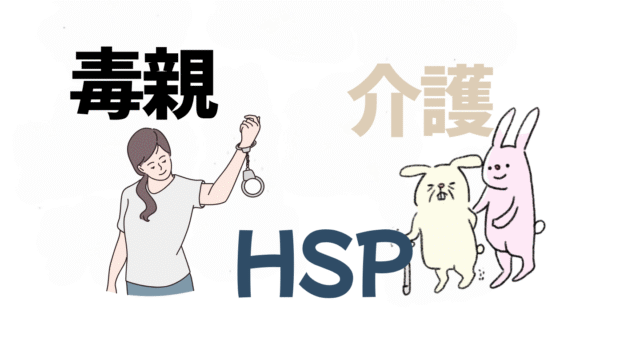ママ友にモヤった時があったなぁと思いだしました。
当時を思い出して 悩める後輩ママに書いてみようと思います。
また、
2人の息子は私立と公立の別の園へ行きました。
その違いも書いてみました。
公立保育園と私立幼稚園、ママ友付き合いの“温度差”を経験してみた

ママ友)公立と私立の違い(保育園と幼稚園)
幼稚園と保育園はいろんなことが違っていました。
うちは長男が幼稚園(私立)次男が保育園(公立)でした。
送迎時のつきあい
送迎時にブランド服を着てくるお母様が多い私立の幼稚園。
子どもとお揃いの方も多くいらっしゃいました。
自分も変な服は着て行けず。。
持っている中でまともな服をチョイスしていました。
巻き髪の奥様も多かった(;´Д`)
ぎりぎりに行って
ササッと帰ってきていました。
ゆっくりと話をしてる感じのママも多くいらっしゃいました。

市立保育園は事務服やスェット姿のお母さんが多かったです(仕事帰り)
父に送迎を頼んでいたため、あまり嫌な思いはせずに済みました。
たまに迎えに行くと
忙しいお母さんが多いため、余計な話もせず
「お疲れ様です~」と慌てて帰られる人が多かったです。
あまりママ友のお付き合いは無かったかも?
公立と私立の違いは大きいですね。
役員会の開催時間など
幼稚園は日中にされていました。
保育園は夜に開催。
面倒だけど役員になるとママ友もできるので良かったです。
私の場合は深く付き合う人は居なくて
その場に行ったら仲良く話す人が数人いた感じです。
働くママの方がパッと決まって
さっと帰ってこれた気がします。
行事など
幼稚園はママと行う行事も多く、大変でしたが、
可愛い姿も実際に見ることができました。
保育園は働くママが多いので行事に参加することはあまりなく、
ラクな反面、寂しい部分もありました。
保育園はそのぶん、写真が多かったような気がします。(当時は良かったですが、後々大変(;’∀’))

働くママ・専業主婦ママとのつきあい
・働いてる
・働いていない
これは幼稚園から中学卒業まで
ずっとモヤモヤする原因でした。
今、選挙でしきりに「今は共働きでないと生きていけない」と
聞くことが多いですが、わたし世代でもそうでしたし
逆に親が専業主婦世代が多かったので
上の年代の人の理解が無かったように思います。
わたしの子育て期と今の若い人の子育て期の違いは
子育てに関する補助などが多いけど
税金が重すぎるし
将来への希望が持ちにくい時代になったと感じています。
みなさん選挙に行きましょう!
(2025.7)
やはり専業主婦ママは暇な時間が多いので
「遊びに行こう」「ランチ行こう」と誘ってくるしイベントをやりたがります。
それはそれで楽しかったし、想い出です。
子どもの悩みも色々聞けたりしますし。
働くママは少し非協力的だったかも?
わたしの働き方はこうでした。
長男のときには正社員→次男は専業主婦→途中で正社員
途中から働いたので 密なママ友会に勧誘されずセーフでしたが
友達は悩んでいました。
早く働きたい・・・
子どもが大きくなる度に働くママが増えていきます。
立場が似てると価値観も近いので
ラクになってきてたような気がします。
同じ働くママでもとんちんかんな人はいましたよー。
ねぇ
どこで働いてるの?パパは?
兄弟の学校を聞いてきてディスったり、、色んな人がいますよね。
ママ友と言う前に
「人として」友達になりたくないママはいました。
ママ友とラクに付き合うために
長い間にモヤモヤはいっぱいありました。
息子同士は気が合うのに
親同士は無理~~~
という場合も多く
「う~む・・」とモヤることもあったけど
働いてたから良かったのかも。
どんな場合でも気分転換のできる場所って大事ですね!
まとめ 公立保育園と私立幼稚園、ママ友付き合いの“温度差”を経験してみた
今、悩んでる後輩ママへこの言葉を贈ります。
ママ友は友達じゃない
わたしはこの言葉で何度も救われました。
それを肝に銘じていれば辛くないと思います。
深いつきあいの「ママ友」はいなくてもいい。
顔見知りで挨拶と世間話するくらいの関係の人がいればいい。
人間関係ってやはり近寄りすぎないことに尽きますね。